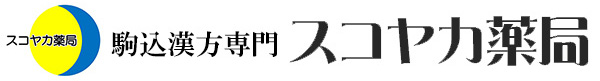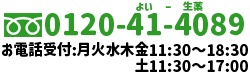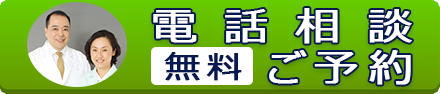漢方薬といえば「薬」と書くので薬ですよね(変な日本語?、笑)
でも、一般的に考えられている薬とは効き方が違うんです。
そのあたりをお話しします。
普通、薬というのは、人工的に合成された成分がある特定の効果を示すものです。
だからその成分が体内に存在して初めて効果をだします。

例えば、頭痛薬なら成分に鎮痛作用や消炎作用があり、降圧剤ならその成分が血管を拡張したり体内水分を排出したりします。そしてそれらの成分が体内で一定量以上ある時に効果を発揮します。
反対に、それらの成分は血中から肝臓に入り、徐々に分解され、体内で成分がなくなってしまうと効果がなくなります。
するとまた悪くなるので、また飲みます。降圧剤、インスリン、ホルモン補充、ステロイド・・・現代医学で使われる薬はすべてこうしたものです。
一方、漢方薬は植物を組み合わせてそれらの成分を抽出した(集めて出した)ものです。だから一般的な薬と違い、「どの成分が何に効く・・」なんて厳密には分かりません。そもそも天然植物の成分なんてきちんとわかっているわけではありません。

そんな漢方薬ですが、効き方は2通りあります。
①ごちゃごちゃに入っている成分がある方向性を持った作用を示す。
②入っている成分が、異常細胞に届き、少しづつ教育することによって異常を是正かする(悪い子が自発的に良い子になるよう再教育をする)
といったものです。
 →
→
ですので、①の場合は、一般的な薬と同じように成分が入っているうちは、「頭痛に効く」とか「熱を冷ます」とか、ある一定の方向を持った効果を示します。しかし、②を期待する場合は、少しばかり飲んだところで異常の是正(悪い子の再教育)なんてできません。
漢方薬のこの②の効き方を知っている方は少ないのではないのでしょうか?
こうした漢方の特性を知っているのと知らないのでは効果に差があって当然です。
さらに①のみの効果しかご存知なく、その次元から西洋薬と漢方薬を比較するのも安直というものでございます・・。
せっかくなら、漢方の特性を十分使い切って、いい効果を出したいですよね!